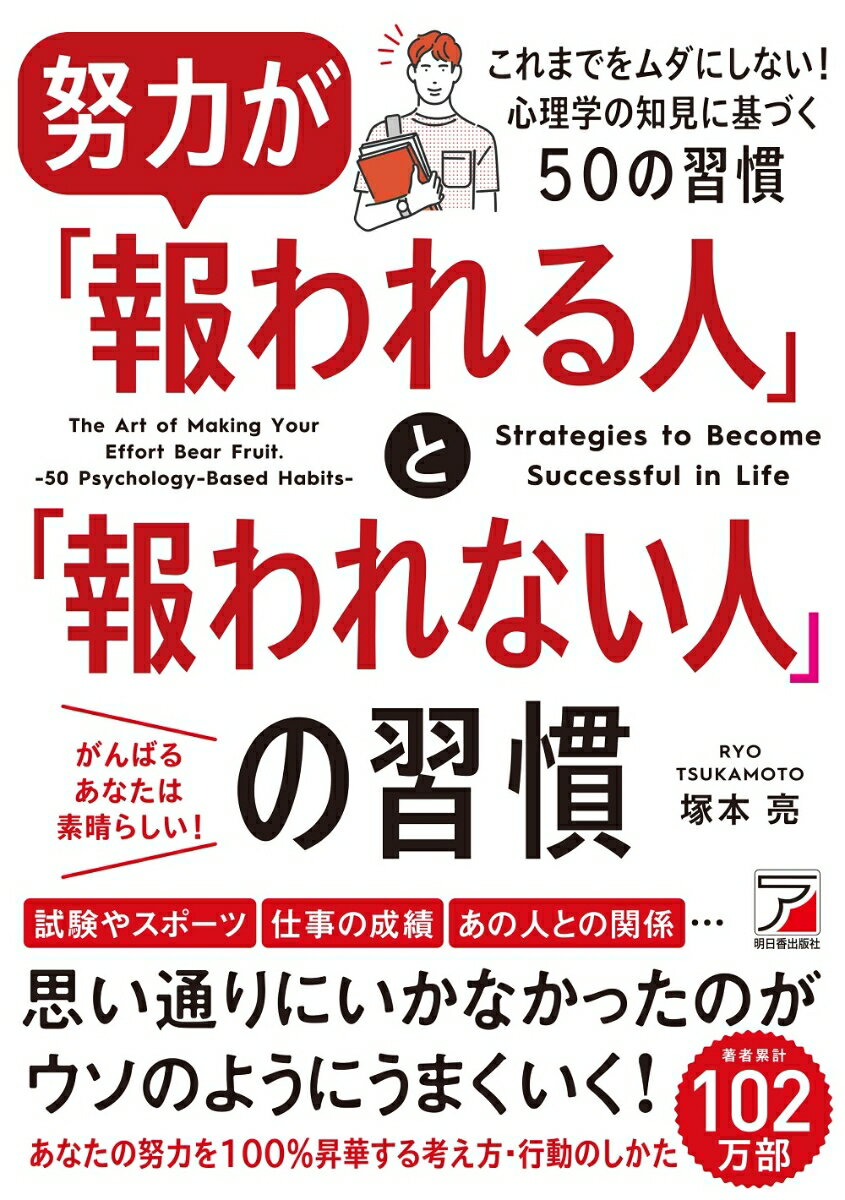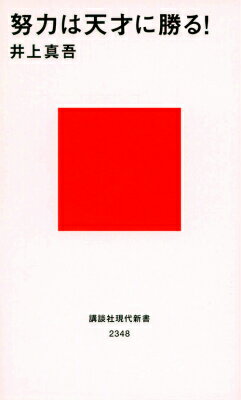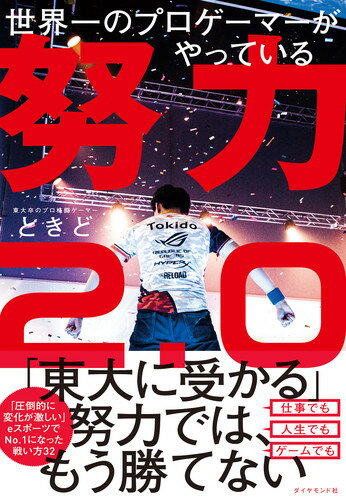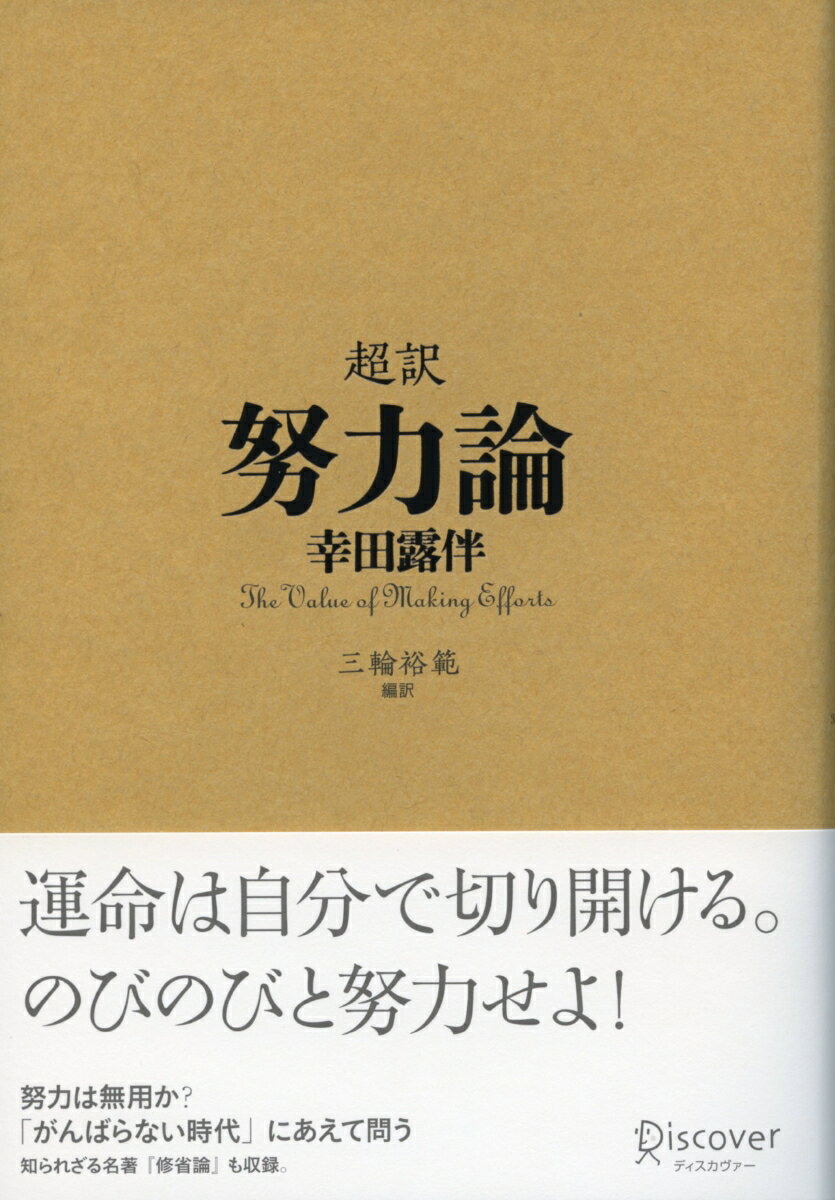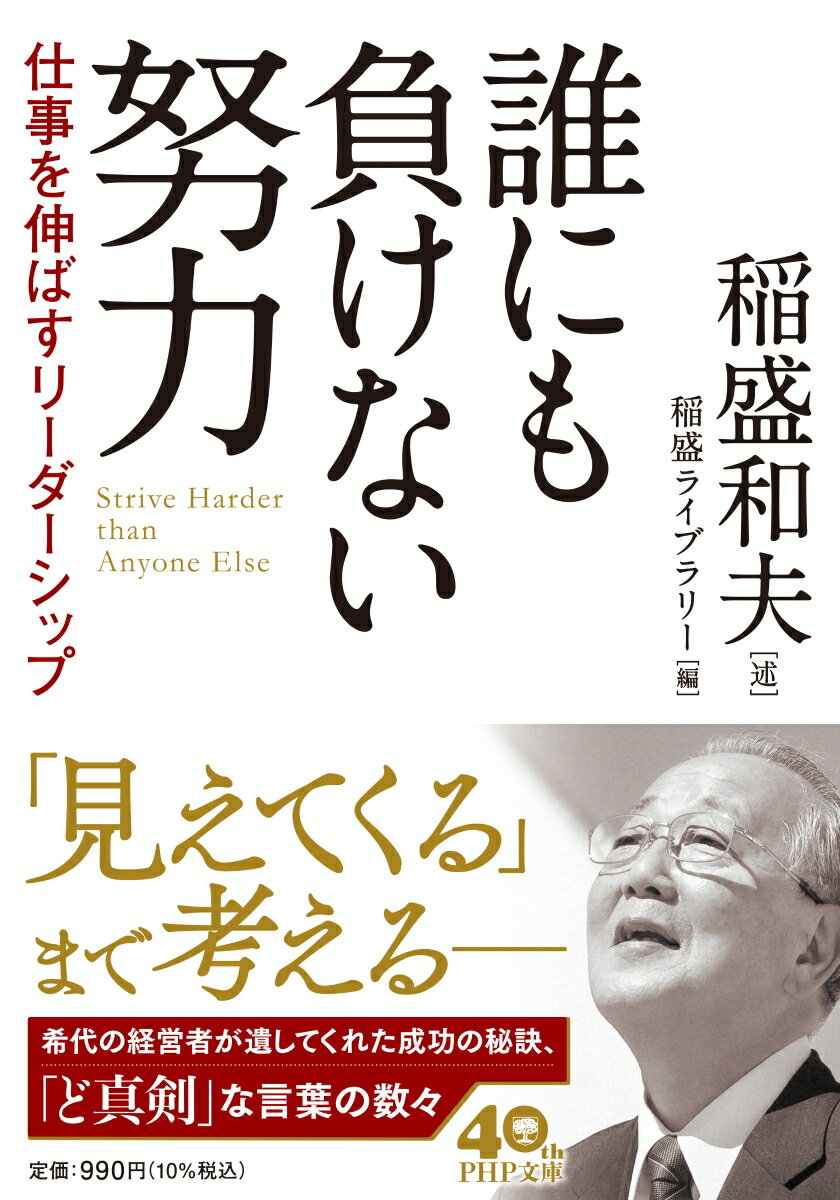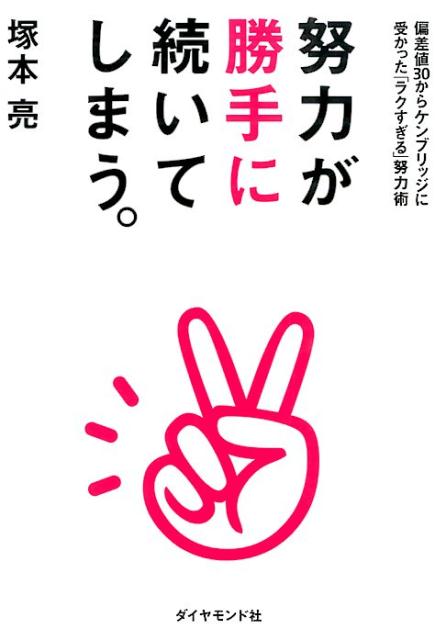2025-04-23
努力を続けたいときに読みたい本8選
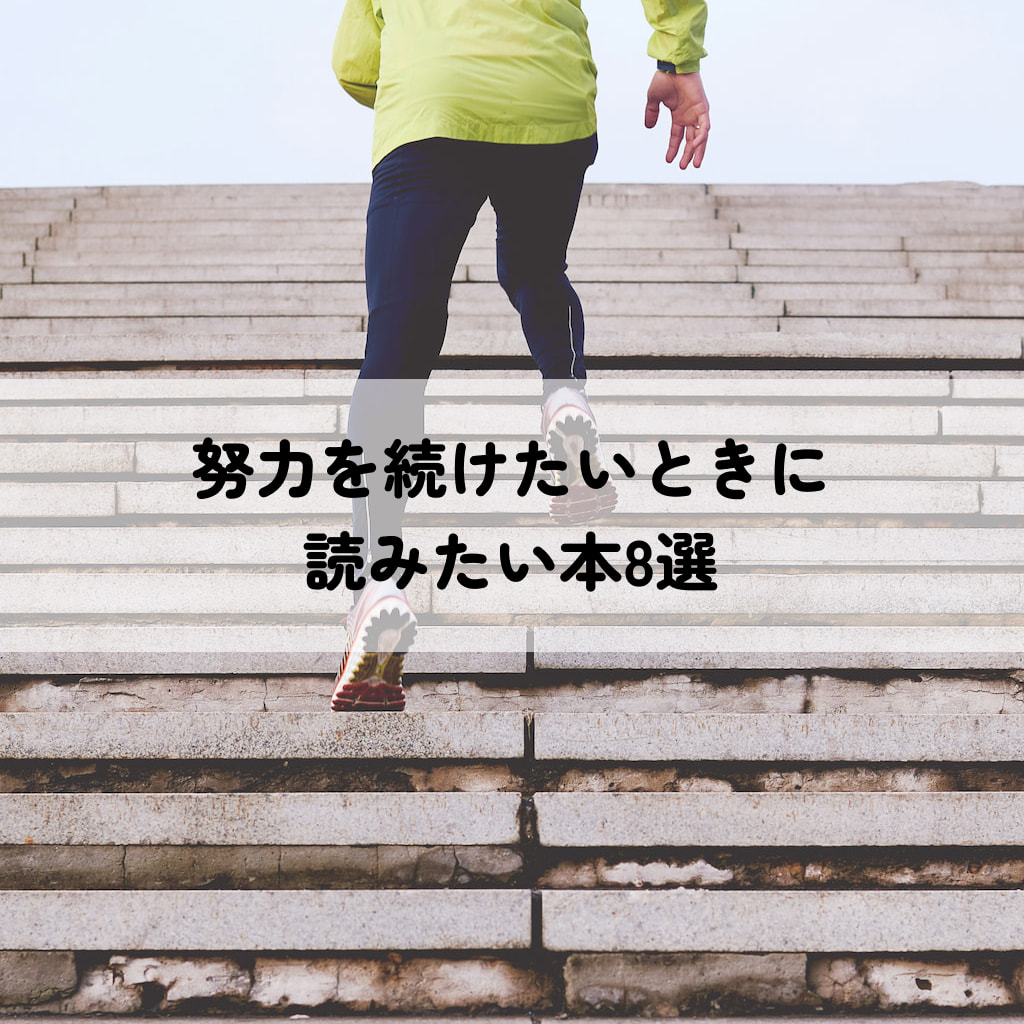
「努力は必ず報われる」
そう言われても、努力の末うまくいかなかった経験があると、どこか素直に信じられない。
一方で、目標を叶えた人たちは、なぜあれほど努力を続けられたのか。そこに理不尽さを覚える。
いったい努力はどうすれば結果につながるのか。
そもそも、自分の今の努力の方向はあっているのか。
自分にあった「努力の仕方」とは何なのか。
このブログでは、そんな「努力」にまつわる疑問や悩みにヒントを与えてくれる本を8冊ご紹介します。
根性論だけで語らない、努力の意味・方向性・続け方を、先人たちの実践と知恵の詰まった本から学んでみませんか?
「頑張るってこういうことかもしれない」と、自分なりの答えが見つかもしれません。
目次
努力は仕組み化できる 自分も・他人も「やるべきこと」が無理なく続く努力の行動経済学(山根 承子)
『努力は仕組み化できる 自分も・他人も「やるべきこと」が無理なく続く努力の行動経済学』(山根 承子 著)の最大の魅力は、努力を「がんばるもの」から「デザインするもの」へと変えてくれる点にあります。 やる気が出なくても続けられる。 失敗しても、すぐに立て直せる。 そんな「現実的な努力」の方法が、行動経済学 の視点から丁寧に解き明かされていきます。 「努力ができない」のではなく、 「努力しづらい環境にいるだけかもしれない」 ──。 そう思わせてくれる、心がラクになる1冊です。
こんな人におすすめ
- 継続が苦手で、努力が長続きしない人
- 意志の力に頼らず、習慣化したい行動がある人
- チームのモチベーションや行動を設計したいリーダー・マネージャー
- 「やらなきゃ」と思いながらも動けない日々に悩んでいる人
この本が教えてくれる大切なこと
- 1.努力とは「意志の力」ではなく、「環境と仕組み」で支えられるもの
- 努力が三日坊主になるのは意志が弱いからではなく、行動経済学的に「継続しにくい環境」があるだけ、という新しい見方が得られます。
- 2.人は本来「非合理的」な存在。だからこそ努力には工夫が必要
- サボってしまう・後回しにしてしまうのは自然なこと。だからこそ、自分の行動パターンに合った努力の方法が重要になります。
- 3.「やる気」よりも「やらざるを得ない状況」をデザインすることが成功のカギ
- モチベーションに頼らず、続ける仕掛けを設計することで、無理なく成果を出せることがわかります。
この本を読んでできるようになること
- 1.継続したい行動を自然と「習慣化」させる仕組みの作り方がわかる
- リマインド・報酬・可視化など、行動を促進させる具体的な方法が学べます。
- 2.自分自身やチームの行動をうまく「設計」できるようになる
- 「サボる前提」「やる気が出ない前提」で行動の選択肢を設計できるので、努力が楽に感じられるようになります。
- 3.習慣を妨げる「バイアス」や「思い込み」に気づける
- ナッジ理論、選択アーキテクチャなどを通じて、 行動経済学 的にどこで失敗しやすいかを理解できます。
- 4.部下やチームの「やる気を引き出す仕組み」をつくれるようになる
- 個人だけでなく、マネジメントや教育の現場でも活用できる行動設計の考え方が身につきます。
努力が「報われる人」と「報われない人」の習慣(塚本 亮)
『努力が「報われる人」と「報われない人」の習慣』(塚本 亮 著)は、ただ「努力は大事」と背中を押すだけの自己啓発本ではありません。 「報われる努力には理由がある」 「報われない努力にも原因がある」 という視点から、成果を引き寄せる思考と習慣を丁寧に解説してくれます。 読むことで、「頑張っているのにうまくいかない」モヤモヤに明確なヒントが見つかり、努力の質を高める一歩が踏み出せるでしょう。
こんな人におすすめ
- 頑張っているのに成果が出ずに悩んでいる人
- 努力のやり方を見直したいと感じている人
- 成果を出している人の習慣や考え方を知りたい人
- 頑張りすぎて疲れてしまっている人
- もっと効率的に、かつ自分らしく目標を達成したい人
この本が教えてくれる大切なこと
- 1.努力の成果は「量」だけでなく「質」と「方向性」で決まる
- やみくもに頑張るのではなく、「自分に合ったやり方」「成果につながる工夫」を取り入れることで、報われる努力になるとわかります。
- 2.成果を出す人には「当たり前にしている思考習慣」がある
- 行動量よりも、「どう考え、どう動くか」の習慣の差が結果を分けることに気づけます。
- 3.努力が報われない人は「自己満足の努力」に陥りやすい
- 頑張っているのに結果が出ないのは、「やったつもり」で終わっていたり、目的と手段がズレているからかもしれません。
この本を読んでできるようになること
- 1.自分の努力の方向が合っているかを見直せるようになる
- 目標とプロセスが一致しているか、自己評価だけに頼っていないかを振り返る視点が持てます。
- 2.成果につながる思考パターンと行動習慣が身につく
- 「自分ごと化」「仮説思考」「フィードバックの活用」など、再現性のある習慣が実践できます。
- 3.自分に合った努力のスタイルを発見できる
- 無理な根性論ではなく、個々人の特性やライフスタイルに合わせた努力の仕方がわかります。
- 4.メンタル・集中力・継続力を高める日々の工夫ができるようになる
- モチベーションが続かない時の対処法や、継続力を支える仕組みづくりも紹介されています。
努力は天才に勝る!(井上 真吾)
『努力は天才に勝る!』(井上 真吾 著)は、「凡人だからこそ夢を叶えられる」という力強いメッセージに満ちています。 「天才じゃない自分に何ができる?」と迷ったとき、 「できるまでやる」「やればできる」という、当たり前だけど大切な原則を思い出させてくれる1冊です。 努力に自信が持てない人こそ、この本で努力は誰にとっても平等な可能性だと気づくことができるでしょう。
こんな人におすすめ
- 才能や環境に自信がなく、夢を諦めかけている人
- 頑張っているのに報われないと感じている人
- 努力をもっと前向きに捉え直したい人
- 子どもや部下に「頑張ることの価値」を伝えたい人
- 継続力を身につけたい、人生を変える一歩を踏み出したい人
この本が教えてくれる大切なこと
- 1.努力は「特別な才能がない人こそ最大の武器にできる力」である
- 生まれ持った才能や環境ではなく、「続ける力」「工夫する力」こそが人生を変える原動力になると実感できます。
- 2.成功のカギは「正しい方向」に「継続して取り組むこと」
- がむしゃらに頑張るだけではなく、努力の方向と継続の工夫が重要であることがわかります。
- 3.人は「やればできる」ことを証明できる存在になれる
- 諦めなければ、目の前の壁は乗り越えられる。自己効力感を育むメッセージが詰まっています。
この本を読んでできるようになること
- 1.「自分には才能がない」と感じる人でも前向きに挑戦できるようになる
- 努力を重ねることがどれほど力になるか、豊富な実例と著者自身の経験から勇気をもらえます。
- 2.正しい努力のプロセスを自分の行動に取り入れられるようになる
- 試行錯誤しながら、自分に合った努力のやり方を見つける重要性を理解できるようになります。
- 3.目標達成に向けた小さな習慣づくりができるようになる
- 毎日の積み重ねがいかに大きな力になるか、継続の大切さが心に残ります。
- 4.挫折や失敗を「成長の一部」として受け止められるようになる
- 成功者も失敗を経験しながら前進しているというリアルな視点を持つことができます。
世界一のプロゲーマーがやっている 努力2.0(ときど)
『世界一のプロゲーマーがやっている 努力2.0』(ときど 著)の魅力は、「努力すればいい」という曖昧な精神論を卒業し、 誰でも実践できる「勝ちに直結する努力」の姿をリアルに教えてくれる点にあります。 一流の舞台で戦い続ける著者の言葉は、 「がんばっているのにうまくいかない」と感じている人にとって、 努力の再定義と再起動のきっかけになるはずです。 「本気で勝ちたい」「変わりたい」と思う人にこそ読んでほしい、現代型の努力論です。
こんな人におすすめ
- 努力しているのに成果が出ないと感じている人
- ゲーム・スポーツ・ビジネスなど競争の激しい分野で勝ちたい人
- 継続が苦手でモチベーションを維持できない人
- 効率的な努力の方法を知りたい人
- 成功者の“リアルな努力”の裏側に興味がある人
この本が教えてくれる大切なこと
- 1.現代に必要なのは、「根性」ではなく進化した努力のやり方
- とにかくやるのではなく、戦略的に努力を設計することで、再現性のある成果が出せるとわかります。
- 2.世界で活躍するためには、技術や知識だけでなく自分をマネジメントする力が不可欠
- 成果を出すための環境づくりや、メンタルのコントロールまで含めて努力は「総合力」であると学べます。
- 3.「継続」「フィードバック」「修正」のサイクルこそが、 成長を加速させる
- 一発勝負ではなく、試行錯誤を繰り返すことの重要性に気づけます。
この本を読んでできるようになること
- 1.時代に合ったアップデートされた努力の考え方を身につけられる
- 気合や根性ではなく、ロジカルに努力の量と質を最適化する思考法が理解できます。
- 2.目標に向かってPDCAを回しながら継続する習慣が身につく
- 行動の振り返りや改善点の洗い出しが、日常的な習慣になるよう導かれます。
- 3.世界一を目指す視点から、競争の中で勝つ努力がイメージできる
- ゲーマーの枠を超えて、ビジネスや勉強、スポーツなどにも応用できる視座が得られます。
- 4.自分のコンディションを保ちながら、成果を出すための自己管理術を学べる
- 睡眠・食事・メンタルケアといった、パフォーマンス維持の工夫も実践的に紹介されています。
超訳 努力論(幸田 露伴)
明治時代に書かれたとは思えないほど、現代の読者にも響く「努力の本質」が、この本には凝縮されています。 静かに、しかし確かに、読む人の背中を押してくれる。 そんな重厚かつ誠実な言葉に触れることで、「続けること」そのものに意味と誇りを持てるようになるでしょう。 華やかな成功体験ではなく、地に足のついた生き方を求めるすべての人に薦めたい一冊です。
こんな人におすすめ
- 努力をする意味を見失いかけている人
- モチベーションの波に左右されず、安定して前進したい人
- 時代を超えて語られる本質的な努力論を知りたい人
- 目の前の結果にとらわれず、長期的な成功を目指したい人
この本が教えてくれる大切なこと
- 努力とは、一時の熱意ではなく日々の積み重ねである
- どんな才能よりも、地道な継続こそが最も確実に自分を高める手段だという、普遍的な価値観を学べます。
- 2.成功にが欠かせない3つのこと
- 努力とは単なる根性ではなく、思考・判断・継続というバランスが取れてこそ意味を持つという視点が得られます。
- 3.成果の大小を決めるのは、目先のスピードではなく正しい方向への着実な歩み
- 成功の本質は、遠回りのようでいて地に足のついた歩みのなかにあると気づかされます。
この本を読んでできるようになること
- 「なぜ努力が必要なのか」を自分の中で深く納得できるようになる
- 一流の知識人による哲学的かつ実践的な思索から、努力の本質を見直せます。
- 一時的なモチベーションに頼らず、自分の芯から努力を続ける意志を養える
- 周囲と比較せず、自分自身の成長に焦点を当てる力が身につきます。
- 3.現代にも通じる人生哲学として、物事に真剣に取り組む姿勢が身につく
- 自己成長・勉強・仕事などあらゆる分野で応用可能な、長期的な視点を得られます。
誰にも負けない努力 仕事を伸ばすリーダーシップ(稲盛 和夫)
この本は、経営者として、そして一人の人間として、稲盛和夫氏が貫いてきた「誰にも負けない努力」の意味を深く学べる一冊です。 それは単なる根性論ではなく、誠実さと原則を貫きながら、困難な局面でも信念を持って挑む姿勢そのもの。 静かで力強い言葉が、読む人の「努力の質」を変えてくれるはずです。 真のリーダーシップと努力の美学を学びたいすべての人におすすめです。
こんな人におすすめ
- 頑張っているのに成果が出ずに悩んでいる社会人・リーダー層
- 努力や仕事の意義を改めて見つめ直したい人
- リーダーシップに必要な人間的魅力や考え方を学びたい人
- 部下や周囲を動かす「背中で語る」リーダーになりたい人
この本が教えてくれる大切なこと
- 1.努力 は才能を超え、人生も会社も動かす最大の力である
- 稲盛氏自身の経験から、成功の裏にあるのは「特別な能力」ではなく、誰にも負けない努力の継続であることがわかります。
- 2.リーダーシップとは人を動かす前に「自分を律する力」
- 強制や支配ではなく、自ら率先して努力を重ねる姿勢こそが、人の心を動かすと学べます。
- 3.「原理原則」に基づいた判断と「利他の心」が成果を生み出す
- 目先の利益ではなく、正しいことを正しくやるという 理念経営の考え方が重要だと気づけます。
この本を読んでできるようになること
- 1.周囲や環境のせいにせず、自らの在り方を正して行動できるようになる
- 「自分が変われば組織も変わる」という視点から、仕事への向き合い方が変わります。
- 2.リーダーとして率先垂範 の姿勢を体現できるようになる
- 人を指導する立場の人がまず実践すべき「努力」「誠実さ」「謙虚さ」の意味が理解できます。
- 3.困難を乗り越える強い心と、継続する力が育つ
- どんな状況でも「あきらめない努力」を継続する心構えと、それを支える考え方が学べます。
- 4.経営者・管理職としての哲学や判断軸が明確になる
- 組織を導くうえでの道徳観・倫理観・理念の重要性を深く理解できます。
努力が勝手に続いてしまう。---偏差値30からケンブリッジに受かった「ラクすぎる」努力術(塚本 亮)
頑張ることに疲れてしまったすべての人へ向けた「努力の再定義書」です。 “がんばる”という感覚を捨てて、スムーズに動ける環境を整えることで、「いつの間にか成果がついてきていた」という未来を作っていく。 そんなラクだけど本質的な努力術が、著者のリアルな経験とともに語られています。 努力が苦手な人ほど、この本で努力のハードルがぐっと下がり、自分をもっと好きになれるかもしれません。
こんな人におすすめ
- 努力がいつも三日坊主で終わってしまう人
- 「やる気」よりも「続けやすさ」を重視したい人
- 勉強・資格・副業などで長期的に成果を出したい人
- 自分に合った習慣づくりの方法を知りたい人
- 成功者の「ラクに見える努力」の裏側に興味がある人
この本が教えてくれる大切なこと
- 1.努力は「気合」や「根性」ではなく、続けやすく設計することがカギ
- 勉強が苦手だった著者が、偏差値30からケンブリッジ大学に合格した過程には、「努力を継続できる仕組み」があったとわかります
- 2.大切なのは「やる気」ではなく、「やりやすさ」の工夫
- 勉強や作業を習慣化するには、ハードルを下げる・ごほうびを設定するなど、脳の性質に合った工夫が効果的だと学べます。
- 3.「努力できる人」になるのではなく、「努力が必要ないほどスムーズに動ける人」になる
- 自己管理のうまさや、行動を引き出す仕掛けが、努力を無理なく続ける鍵であることに気づけます。
この本を読んでできるようになること
- 1.勉強や仕事に対して「続けやすい形」に分解して取り組めるようになる
- 1日5分、やる前に準備だけ、など心理的負担を減らす工夫が身につきます。
- 2.継続のコツを「意志」ではなく「環境」で支えるようになる
- タイマーを使う、学習の見える化をする、SNSで宣言するなど、行動を促す環境デザインが学べます。
- 3.努力を「楽しい」「気持ちいい」と感じられるようになる
- ごほうびを設定したり、目標を細かく刻むことで達成感を味わいながら前に進めます。
- 4.自分に合った勉強法・習慣化の方法がわかる
- 努力の型は1つではないと知り、自分にフィットする方法を柔軟に取り入れられるようになります。
マッキンゼーで25年にわたって膨大な仕事をしてわかった いい努力(山梨 広一)
この本は、努力を「感情」ではなく「構造」でとらえ直す視点を与えてくれます。 25年間マッキンゼーで超多忙な日々を送りながら、著者が辿り着いたのは、頑張りすぎないための努力の技術。 努力は「量」でも「気合」でもなく、「設計された知的行動」だというメッセージは、 多忙で悩みを抱える現代人にとって、大きなヒントとなる一冊です。
こんな人におすすめ
- 頑張っているのに成果が出ず、モヤモヤしている人
- 戦略的に努力できるようになりたいビジネスパーソン
- 無駄を省き、より高い成果を出したい人
- 自分の努力の質を見直したい人
- 忙しくても「意味のある努力」に集中したい人
この本が教えてくれる大切なこと
- 1.成果につながる努力には「正しさ」がある
- 闇雲に頑張るのではなく、「どこに、どれだけ、どうやって」力を注ぐかが努力の質を決めるとわかります。
- 2.「無駄な努力」に陥る原因は、目的や手段の不明確さ
- 成果が出ないときは、自分の努力の構造(目的・手段)を疑ってみることが必要だと学べます。
- 3.長期的に成果を出す人は、「手応えのある努力」に集中している
- 小さな成功を積み重ねることで、自信とモチベーションを維持できる努力設計が大切であると気づけます。
この本を読んでできるようになること
- 1.自分の努力の方向性を整理・再構築できる
- 目的・目標・手段を因数分解し、ゴールに近づくためのプロセスを最適化する思考法が身につきます。
- 2.仕事・学習・人間関係など、あらゆる行動において「いい努力」を選べるようになる
- 感情や惰性ではなく、論理と構造をもとに努力をデザインできます。
- 3.成果を出すための思考の習慣が身につく
- 仮説・検証・改善・継続という努力のスタイルが実践できます。
- 4.「がんばっているのに報われない」状態を脱出できる
- 努力の方向がズレていないかをチェックし、「修正する力」が得られます。
最後に
「努力が続かないのは、自分の意志が弱いから」 そんなふうに責めてしまうことはありませんか?
今回ご紹介した8冊は、努力を根性論で終わらせず、仕組みや考え方、習慣として日常に落とし込むためのヒントが詰まった本ばかりです。
やる気に頼らず、楽しみながら続ける方法。
正しい方向へ、無理なく力を注ぐ工夫。
そして、自分らしく努力を重ねる心の持ち方。
努力が自然に「続いてしまう」状態をつくるために、 あなたにとってしっくりくる1冊が、この中にきっとあるはずです。
「がんばりたい」あなたを支えてくれる1冊と出会えますように。